
| シネマ&ブックレビュー 話題の映画や本を紹介します |
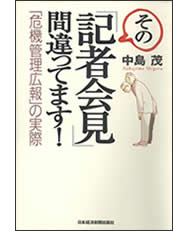
は広がってきた。それは同時に“企業が社会から糾弾されるリスク”もまた全方位に広がったことを意味している。
本書は現代社会で「欠陥商品、工場事故、災害、特許紛争、法令違反、情報流出、社内不正など、実に様々なリスク」に取り囲まれる企業に対して「危機管理広報について、平時に準備しておくべきことから緊急時の対応まで、実践的な観点からポイントをまとめた」ものである。
本書の冒頭で掲げる“企業広報の心得Ⅰ”は以下の言葉である
「企業は世間の『反感』を買ってはならない」
なぜならば「反感」によって取引先や消費者が離れるのみならず、現代では「世間の『反感』に応えて行政そして司法も厳しく対応する」からだと本書は言う。行政や司法が世間の(ある意味)感情で動かされることが正しいのだろうかと一瞬、困惑すると間もなく、次の章で著者はその正当性を「『コンプライアンス』の本当の意味」から説明する。
一般的に法令順守と訳されるコンプライアンスだが「本来は、『相手の願いや期待に応える』という意味(Oxford Dictionary of English、研究者「新英和中辞典」など)。」であり、著者はさらに進んで「相手の身になって考え、行動することがコンプライアンス」だと読み解く。相手の願いや期待は人間によって何百通りあるのか、ここでコンプライアンスが意味する“果てしなさ”に愕然とする企業担当者も多いに違いない。
さらに著者は、2009年3月期からJSox法が施行されるなど、企業の関心が高い内部統制システムについても関連づけて説明する。つまり、2006年5月に施行された会社法により全ての企業に求められる“会社の業務の適正を確保する体制”とは、「本来の意味でのコンプライアンス、つまり消費者、従業員、社会、株主それぞれの期待に応える、というコンプライアンスの実現を確保するための体制」であり、だからこそ「法律が『業務の適法』といわず、『業務の適正』という表現を使っている」のだ!
本書では近年における数多くの企業不祥事の実例をもとに、広報対応の良し悪しと結果の差異を紹介し、具体的な対応としては危機管理広報の3つのポイント「謝罪、原因究明、再発防止」から経営トップや広報担当者が取るべき具体的な対応「伝える技術」を伝授している。
さらに近年の広報では伝えるメッセージ自体にも事前の顧問弁護士等による法的視点からの検討「リーガルチェック」が不可欠であるとし、「株主代表訴訟」「製品改良の発表」(製品改良するということは、以前の製品に問題点があったと認識される恐れがある!)「PL(製品責任)裁判の和解」「サプライヤー・チェーン・リスク(原材料等の調達先での企業不祥事等による企業リスク)」「顧客情報流出」「社員の不祥事」など、近年は“一般的”とさえ言えるほど頻繁にマスコミをにぎわせる企業不祥事発覚時の広報についても個別に説明を行っている。さらに最終章では実際の記者会見をどのような手順で行うか、スタートから終わり方まで、まさに“手取り足取り”教えてくれる。
本書の中で著者は、企業は世間に“わかってくれる”と期待してはならない。黙々と誠実に対応する「日本企業の美徳」は通用しなくなった現代を、著名なエッセイスト山本夏彦氏著書の一文「事実があるから報道があるのではない。報道があるから事実があるのである」が言い表していると語っている。
本書を通じて、企業と消費者とは互いが直接的な利益関係者でありながら、現在も多くの消費者はマスコミを通して企業とつながっている、一方でインターネットなど個人(彼らもまた企業人であることも多い)が直接的に企業を攻撃することができるツールの発達、さらにはTVを中心としたマスコミ報道と世間の感情が必ずしも一致していない現状などに思い至るとき、企業のCSRとは“いかに隣の人と直接的につながり、(過去の日本では言葉がなくても存在した)信頼関係を復活するか”私たち個人が抱える問題と根っこの部分が同じであることに気づく。
本書は2007年2月に発行された。弁護士として企業のコンプライアンスに関わってきた著者の経験が分かりやすく豊富に盛り込まれ、2009年7月現在でも、コンプライアンスや広報に新たにかかわる担当者にとって必読の実践書といえる。