
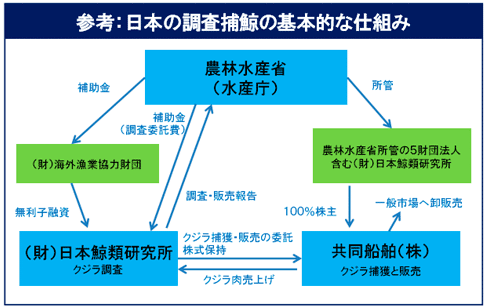
| 注:上記はCSRマガジン編集部が補足資料として「刑罰に脅かさ れる表現 の自由」(グリーンピースジャパン[編] 海渡雄一[監 修] 現代人文社)掲載 チャートを元に作成してい ます。 |
2008年に日本経済新聞が実施した調査では、20代の日本人のうち鯨肉を食べたことがあるのはわずか12パーセントであることが明らかになった。一方で、日本リサーチセンターが2006年に実施した調査では、日本人の95パーセントが鯨肉をほとんど食べないか、まったく食べたことがないことが報告された。
水産庁のデータでは、2010年9月には日本の冷凍鯨肉の貯蔵量は過去最高の5,670トンに達したことが示唆されている。学校そしてスーパーマーケットでの消費促進の取り組みにもかかわらず、この数字は1999年に初めて記録がとられて以来最高のレベルであった。
東北大学の石井敦准教授は「捕鯨産業はその存続のために補助金に依存するようになり、官僚がその維持を固く決意している」と指摘した。
「日本の官僚制度では、補助金と管轄権を失うことは非常に悪いことであると考えられています。ICRに準備されている天下りのポストは水産庁にとって、とても重要なのです」と石井准教授は述べた。
「捕鯨問題に大金がからんでいるのであれば、政策論争の対象に取り上げられるでしょうが、わずかな補助金が拠出されているにすぎません。しかも、捕鯨問題はナショナリズムの文脈で捉えられていて、なかなか正面切って議論しにくくなっています。そうした中で誰が捕鯨を止めようとするでしょうか?」
日本の捕鯨外交の真の目的は商業捕鯨の再開ではなく、科学的捕鯨の継続だと石井准教授は指摘している。彼によれば、商業捕鯨の再開は「日本の捕鯨支持グループにとっては最悪のシナリオ」であるという。
「商業捕鯨の一時禁止が解除された場合には、科学的捕鯨を正当化する言い訳が存在しなくなり、科学的捕鯨活動に対して提供されている補助金と無利子融資は削減され、最終的には廃止されることになるでしょう」と石井准教授は述べた。
「報告された鯨肉の貯蔵量は過去最多であり、データ収集の対象にはならなかったその他の場所におそらくもっとたくさん貯蔵されていることでしょう。捕鯨産業が補助金と融資を失えば、需要は存在しないのですから産業そのものが破綻に直面することになるでしょう」
捕鯨産業が使う捕鯨の必要性についてのもう一つの説明は「食糧安全保障」という日本が長期にわたって掲げている目標である。アデレード大学のラサスはこの概念を支持している。
「食糧安全保障の問題は多様化に関するものにほかなりません。日本が本マグロや輸入代替品などの食料を手に入れることができなくなったら、どこから肉類を手に入れればよいのでしょうか?日本人は鯨肉についても可能性を残しておきたいのです――この可能性を日本人は手放したくないのです」
日本政府は食糧安全保障の問題を「極めて深刻に」受け止めているとICRのインウッドは指摘している。そして捕鯨が制限されているために、しかもその制限のみを理由に鯨肉の消費が減少しているというのがインウッドの主張である。
「日本政府はおよそ3,000から4,000トンの鯨肉の在庫を恒久的に貯蔵しています・・・牛肉の備蓄はおよそ60,000トン、豚肉の備蓄量は平均すると50,000トンです。こうした[反捕鯨]グループは日本人が牛肉や豚肉を食べたがっていないとでも言っているのでしょうか?」
「一例を挙げれば、日本国民のわずか5パーセントしか鯨肉を食べていないというのが反捕鯨グループのお気に入りの主張です・・・[しかしながら]最低限の人数の人々が特定の肉を食べているかどうかという判断に基づいた反捕鯨グループの主張はまったく滑稽です」。カンガルーを食べるオーストラリア人の2倍の数の日本人が鯨肉を食べているということを示唆するデータを引き合いに出しながらインウッドは述べた。
日本の捕鯨政策はむしろ国際的な日本の漁業権の保護に対するこの国の懸念を背景にしていると言うその他のアナリストもあった――世界最大の海産物消費国の一つにとっては重要な問題なのである。
「“捕鯨をめぐる戦争”はむしろ捕鯨ではなく――国際的な漁業に対する日本の権利に関する問題なのです」とテンプル大学日本校のキングストン教授は語った。
「もし日本が捕鯨問題についてその主張を曲げて、各国が保護区を主張し日本のアクセスを妨げることを許したとしても、これが捕鯨だけの問題ならば実際には多くの人々がこれで困るような事態にはなりません」
「しかしこれがマグロやその他の日本人のお気に入りの鮨ネタということなら、被害を受ける人々が現れ、多くの注目を集めることになるでしょう。捕鯨をめぐる争いでは、日本人は自らの海外における漁業権を放棄するつもりがないという原則を世間に認めさせようとしているのです」
海外での日本の捕鯨に対する敵意を考えると――日本国内での捕鯨活動はこれほどの注目を集めてはいない――解決策への見通しは暗いようである。しかしながら、最終的には解決策がまったく想像もできないような所から登場するという楽観的な見方は依然として存在している。
「日本の捕鯨船団が老朽化しているというのが重要な問題です」とキングストン教授は述べた。
「この船団にはどうしようもなく近代化が必要ですが、現在の国家財政のもとでは捕鯨船団の性能改善のための予算の大部分を日本政府が正当化するのはまず困難なことでしょう」
この理論を裏付けているのが日本の捕鯨船団の出発の遅れだ。『否定的な評判を背景に日本の船団は代わりになる給油船を手配するのに苦労している』というグリーンピース・ジャパンによる主張の真っ只中で発生した遅延である。
「共同船舶はこれまで利用していた給油船を失いました。ところが、国際的な非難の対象になっている捕鯨活動に巻き込まれるリスクを冒そうとする船主を見つけるのに苦労しているのです」とグリーンピース・ジャパンの花岡和佳男はジャパンタイムズ紙でこう述べたと伝えられている。
日本は「面子を保った形でのその南氷洋捕鯨からの撤退」の方法を探しており、船舶輸送規制の変更が機会を提供することになるかもしれないというのがかつてのシーシェパードの活動家のピーター・ベチューンの考えである。
「南極海における船舶を管理する新たなルールが間もなく施行され、その規定の一つは重油の利用を禁止するというものです。南極海ではディーゼルエンジンで動く船舶の利用が義務づけられるようになり、[日本の調査母船である]日新丸はディーゼル燃料では駆動しないため、日本は船舶に新たな装備を施さねばならなくなるでしょう」とベチューンは語った。
「規制の二つ目として、船舶は二重船殻構造であることが義務づけられることになります――船殻は事実上一重でなく二重でなければなりません。全船団についてこれを実現することは一大事業となることでしょう――それには3億米ドルのコストがかかりますが、捕鯨は年間わずか5,000万米ドル規模の事業なのです」
ベチューンはさらに加えてこう述べた。「日本はこれまでもそうであったように新たな規制の無視を選ぶこともできます。しかし、これほど多くの世間の厳しい目にさらされている今回はこれはより難しい選択肢でしょう。もし私が日本の立場ならば、南極での捕鯨を今後5年間にわたって停止することを考慮することでしょう」
「南極海での捕鯨からの撤退はこの地域を自国の裏庭であると考えているニュージーランドとオーストラリアが提起する問題から発する危機を収めることになるでしょう」
最近のIWCでの交渉で日本が見せた妥協の意志をベチューンは前向きな兆候であるとも指摘した。
日本側の譲歩に対する反捕鯨グループの反応に日本政府は「落胆している」とICRのインウッドは述べた。この譲歩の内容は南極海での日本の割り当ての半減も含むものであった。「反捕鯨国の大部分は一切の妥協案を提示しませんでした」とインウッドは指摘した。
27カ国と一つの地域で構成される分離捕鯨支持グループの設立に対して日本が最近圧力をかけたと共同通信社は報じたが、この事実はIWCに対して日本が苛立ちをつのらせていることの兆しであるかもしれない。
しかしながら、ICJが日本の調査捕鯨にとって不利な裁定を下した場合には、この国の捕鯨政策はその管理を離れることになるかもしれない。Diplomat誌が聞き取り調査を実施したアナリストたちはそのような見通しの可能性はほとんどないと回答したものの、「裁判が継続する間は捕鯨を禁止する経過措置をオーストラリア政府は求めることができるでしょう」とオーストラリア国立大学のドナルド・ロスウェル(Donald Rothwell)教授は語った。
「経過措置を求めるかどうかその決定権は現在オーストラリア側にあります。この措置は事実上国際的な強制命令です。捕鯨シーズンの真っ最中にこの措置が実行されればもっとも時宜を得ていることになるでしょう」とロスウェル教授は述べた。
「外交上の解決を止める手立てはありません。こうした国際裁判所での訴訟をどう見なすか――その一つはこうした裁判事件は法的戦略であるのと同じくらい政治的戦略であるということです――ときとして法秩序のもとでは負けても、最終的には政治で勝つことができるかもしれません」
こうして鯨をめぐる戦いを整理してみると「やはりゴジラは国際的な捕鯨の舞台ではなく映画館で再上映するようにしてほしものだ」と中立的な観察者たちは間違いなく望むことだろう。