
Q: 高瀬さんが運営する世界マメナジー基金は、個人や法人からの「1000円の寄付につき、必ず1Wの太陽光発電などの再生可能エネルギーを増やす」、普通の個人の力で日本に自然エネルギーを増やしていくプロジェクトと伺いました。
これまで、日本エネルギー経済研究所をスタートとして、エネルギー問題では日本の最先端にいらっしゃる先生方と接して研究を続ける一方で、2000年ぐらいからは自然エネルギーの普及を考えるようになり、2005年には個人に向けてグリーン電力証書を販売するCO2 free.jp Projectにも参加しました。
長年、エネルギー問題に携わるなかで感じたことは、個人がエネルギーを選ぶ仕組みをつくれないだろうかということでした。
古くから国の方針を決めるには、トップダウンとそうでない二つの方法があります。 トップダウンは “専門家が考えて決めるから、市民は何も考えずに暮らしてください”という考え方、もう片方は“市民も考えて選択すべき”という考え方です。 これまで国のエネルギー政策には個人の意思がかかわりにくい、つまり“トップダウン”が基本でした。
私は全てのエネルギーには良いところと悪いところがあると思っています。 原子力発電はCO2を下げるためにはとても良いエネルギーですが、ゴミ廃棄や安全性への住民不安から、立地に苦労しています。自然エネルギーの一つである風力発電にしても、安全性などの問題はありませんが、騒音があるという人もいます。
特に原子力発電というのは、かつてエネルギー研究に取り組む人間にとって(世界を良くするための) “夢の技術”でした。私が師事する先生方にも原子力に対する大きな夢を持っている方がいらっしゃいます。
今現在、私は再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電に最も期待しています。 けれども、ひとつの技術を“夢の技術”として決めつけていいのかという思いもあります。それぞれ、良いところ、悪いところがあるのだから、私の意見はただの“一票”であるはずです。
普通の人たちの判断力を馬鹿にしてはいけない。(エネルギー問題が難しいといっても)分かり易く説明すれば身近な問題として判断いただけるはずです。 社会を良くしたいという思いはトップダウンを推進する人も同じなのですが、私は一人ひとりの個人がエネルギーを選べる“投票用紙”を作りたい、と思いました。
現実的に太陽光発電を家に設置するには200〜300万円(標準的な3kWの場合)ぐらいかかりますし、マンション住まいでは自由に設置出来ません。個人の意思さえあれば、ダイレクトに世界中にでも自然エネルギーが増える仕組みが良いということで世界マメナジー基金を設立しました。これまでは1000円単位で寄付いただくことが多かったのですが、現在、1円単位でできる、いわば現代のベルマーク的な仕組みを作ろうと奮闘しています。ちょっとした個人の選択行動で未来に“投票”出来る、そんな仕組みを実現したいというのが今の思いです。
| 特定非営利活動法人 世界マメナジー基金 http://www.mamenergy.org/index.html マメナジー(mamenergy)は、My Actions for My ENERGYの略)。 個人(または法人)からの小さな寄付、できる範囲のActionsを集めることで、自然エネルギーの育成等、持続可能な社会の実現を目指す。寄付または商品の購入により「1000円あたり1Wの太陽光発電などの再生可能エネルギーを増やす」ことができる。
|
Q: 確かに太陽光発電が良さそうだと思っても、日本で個人が導入するには今まではハードルがありました。
例えばドイツの場合は、太陽光発電で発電された電力を全量電力会社が高値で買い取る義務があり、太陽光発電はおよそ20年間持つといわれていますが、例えばドイツでは約8年で投資回収できる---つまり12年間はタダで使えるだけではなく、儲けがでる!---と言われています。
一方、日本の場合、補助金なしで投資回収に28年間かかります。2009年1月からは1kWあたり7万円の補助が出るようになり、さらに2009年11月からは家庭の太陽光発電から発生する余剰電力(自家消費分を除く)を電力会社が48円/kWh(注1)で買い取る新制度がスタートしました。その結果、現在の投資回収年数は補助金ありで25年、余剰電力を買い取ってもらう分も含めると16年と言われています。(注2)
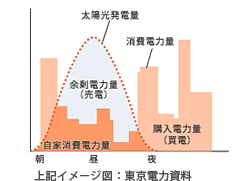 (注1) 設備容量が最大出力10kW未満で、かつシステム価格が70万円(税抜)/kW以下の場合。なお、太陽光発電以外の発電設備等を併設している場合の買取価格は39円/kWh程度となる。また、太陽光発電以外の発電電力を太陽光発電ができない夜などに消費した場合はその分を電力会社に支払うこととなる。 (注1) 設備容量が最大出力10kW未満で、かつシステム価格が70万円(税抜)/kW以下の場合。なお、太陽光発電以外の発電設備等を併設している場合の買取価格は39円/kWh程度となる。また、太陽光発電以外の発電電力を太陽光発電ができない夜などに消費した場合はその分を電力会社に支払うこととなる。(右イメージ図を参照) (注2) 家庭で標準的な太陽光発電3.5kWシステムで約245万円を元に、 245万円―[補助金 3.5kW x7万円=24万5千円]=初期投資約220万円で試算。 |
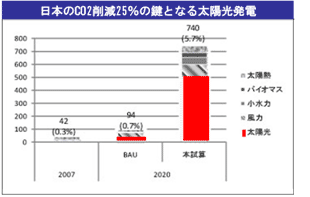 高瀬氏の試算によれば、CO2削減25%(1990年比)は決して無理ではない。現実的な範囲で省エネと再生可能エネルギーの取り組みを最大限進めた場合、2020年には1990年比でマイナス27%が可能となる。その際の鍵となるのは再生可能エネルギーで、最終エネルギーに占める割合が5.7%(2007年は0.3%程度)のトータル1億kW(2007年は約400万kW)まで増える必要があり、そのうち太陽光発電は8割の7,900万kW(2007年は約170万kW)と試算されている。 高瀬氏の試算によれば、CO2削減25%(1990年比)は決して無理ではない。現実的な範囲で省エネと再生可能エネルギーの取り組みを最大限進めた場合、2020年には1990年比でマイナス27%が可能となる。その際の鍵となるのは再生可能エネルギーで、最終エネルギーに占める割合が5.7%(2007年は0.3%程度)のトータル1億kW(2007年は約400万kW)まで増える必要があり、そのうち太陽光発電は8割の7,900万kW(2007年は約170万kW)と試算されている。 |
Q: 高瀬さんは“環境問題は省エネと再生可能エネルギーの両面から取り組むべき”と仰っています。しかしながら、これまで日本では個人が再生可能エネルギーに貢献するという意識が低かったようにも思います。
実はIEA(国際エネルギー機関)が2008年に出した再生可能エネルギーに関するレポート(文献2)によれば、世界各国ごとに太陽光発電システムのコスト(または利益)と導入率の割合から見ると、日本はむしろ導入率が高いという結果が出ました。
例えばドイツでは2000年に再生可能エネルギーを高く買い取らないといけないという法律が出来てから、飛躍的に太陽光発電システムの家庭への導入が進みました。 つまり、個人が“儲かるから”太陽光発電を利用しようということですね。 一方で日本は世界でいち早く太陽光発電技術に取りくんだにもかかわらず、その後は一般へ普及するための政策が遅れ、海外先進国と比較すると日本で太陽光発電を導入する際のコストはいまだに高いです。その割に導入率が高いということは、むしろ日本のほうが個人の環境意識が高いといえますね。
しかし、再生可能エネルギーを大量に電力システムに取り入れるには、ハードルがあります。日本だけでなく、世界的に、発電は大規模であればあるほど効率的であったという時代があり、その時代に、大きな発電所を中心とした電力システムが確立されました。末端にいる多くの利用者の変動する需要に確実に応えるために、全体のシステムをコントロールするというシステム運用が行われてきました。その確立したシステムの末端(家庭)から、太陽光発電による電力が“逆に”流れてくると、いわば変電所の先にノイズが入ってしまう、センターの役割を持つ発電所からだけでなく、変電所や末端の発電から発電所へと逆流するような、従来と異なる流れでコントロールすることが難しいということになります。
しかしながら、最近では新たにスマートグリッド(電力系統にIT技術を活用し、電力の需要と供給を効率・安定化する仕組み)が世界的に注目されています。発電システムへの影響という問題点をクリアできる新技術の登場で、今後さらに太陽光発電を含む再生可能エネルギーの普及が進むと期待しています。
