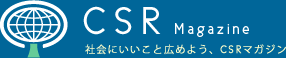識者に聞く
新しい価値観で未来を創り直すために「裸足の大学」インドのベアフット・カレッジに学ぶこと
地域の共同体が主体となって全てを決める
Q ベアフット・カレッジの取り組みはインド以外の国にも広がっています。国によって、やり方を変えている部分があるのでしょうか。

ベアフット・カレッジの主役は地域の共同体の人々。そう主張するバンカー・ロイ氏は自らをあくまでもスタッフの一人と位置付けている。今回のブループラネット賞も個人ではなくベアフット・カレッジという団体としての受賞である。
ロイ:世界中で何百万という村が全く灯りのない生活をしています。基本的なアプローチは同じです。まず地域の共同体の人たちと対話し、交流し、地域社会の共同体自身が導入することに決めた問題解決策に対して、責任をもって運営してもらいます。
インタビュー時撮影 ロイ氏写真掲載「ベアフット・カレッジの主役は地域の共同体の人々。そう主張するバンカー・ロイ氏は自らをあくまでもスタッフの一人と位置付けている。今回のブループラネット賞も個人ではなくベアフット・カレッジという団体としての受賞である。」
具体的にいうと、最初のステップは、村人たちに集まってもらって会議を開きます。その中で、例えばソーラー発電を導入する場合に、村ではいくらの料金を払う気があるのか、料金設定を含めて話し合いをしてもらいます。通常は、それまで灯りのために支払っていた灯油代とかディゼールとか、ろうそく代とか、大体月当り5ドルから10ドルの範囲内で料金を設定されます。
次のステップとして、ワークショップができる部屋を確保してもらいます。そこに研修生(おばあちゃんたち)を集め、ソーラー発電で一番手間がかかる修理やメンテナンスなどのトレーニングを行います。他国の村の場合は、大抵はおばあちゃんたちを6カ月間インドに連れてきてトレーニングをしています。
3番目に、村の中にきちんとソーラー発電による灯りの使用料を徴収できるよう監督する委員会を設けてもらいます。使用料の30%をエンジニアとしてトレーニングされたおばあちゃんたちが給与としてもらいます。そうすることでおばあちゃんたちが技術的にも財政的にも村の中で自給できる、あるいは自立できるシステムが出来上がります。おばあちゃんたちは外部の専門家に依存することなく修理からメンテナンスまで全部行える能力がありますので、5年間大学で教育を受けたエンジニアよりもよほど実地的なスキルを身に付けていることになります。以上が、ベアフット・カレッジの持続可能な問題解決策です。
| インド以外の各地に広がるベアフット・カレッジによる太陽光発電 |
 |
| 2001年以来、33ヵ国、1,014村の34,500住宅で、698人のおばあちゃんエンジニアによって太陽光発電が利用されている。(資料はBarefoot Collegeから) |