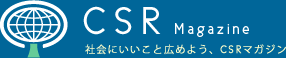識者に聞く
東日本大震災における救援と復興への取り組みPart2[後半]:「企業とNGOの協働」と「気仙沼・大島モデル」
拓殖大学国際学部 長坂寿久教授に聞く―NGOと自治体および企業との協働<<企業・NGO・自治体のユニークな協働「気仙沼・大島モデル」>>
この島の復帰・復興に向けて、企業とNGOと地元自治体組織の3者の協働によるプロジェクトが進展している。このような事例は他の地域でも起こっているが、実にユニークな新しい取り組みなので、筆者はこれを『気仙沼・大島モデル』と呼んでおこうと思う。
「企業」は、国連グローバルコンパクトへの署名企業が対象である。国連グローバルコンパクトとは、2000年にアナン前事務総長が提唱したもので、企業のCSR(企業の社会的責任)活動と、国連活動への参加促進を図るため、人権・労働・環境・腐敗防止の4分野10原則を支持することを宣言(署名)する仕組みである。日本では現在175企業・団体が署名している。
富士ゼロックスは大島で新人研修の一環として、Civic Forceと現地自治体組織と協働して瓦礫処理ボランティアに取り組んできたが、この方式が、9月以降は国連グローバルコンパクトの署名企業(グローバルコンパクト・ジャパン・ネットワーク/GC-JN)のプロジェクトとして開放され、他の企業も参加しながら、より多角的かつ継続的な社員ボランティアを送り込む仕組みへと拡大されることになった。状況を見ながら、今年度中(2012年3月末)は継続派遣を実施する予定である。GC-JNは、大島支援プロジェクトと共に、亘理町にも同様の署名企業の社員ボランティアの派遣プロジェクトに取り組んでいる。
「地元」側では、大島の町内組織(気仙沼大島振興協議会の大島地区災害対策本部)が受け入れ、作業現場の指揮は地元の救援チーム(おばか隊)が当たる。地元での調整については国際的に活動を行っている公益社団法人Civic Force(シビックフォース)(緊急即応チーム)が担当する。Civic Forceは、今後連携企業を増やすとともに、必要に応じて受け入れをする地域を拡大する意向を持っている。
Civic Forceは4月から、NPOなど7団体と「パートナー協働事業」を展開してきた。同事業は特定地域にとらわれず、専門性のあるNGOと連携して生活再建支援を行う、例えばボランティア用宿泊施設を日本財団ROADプロジェクトと静岡県ボランティア協会などと共に立ち上げている。社会福祉協議会や地方青年団、NGOなど約50団体で組織される「遠野まごころネット」の立ち上げや、食堂事業の開始などにも参加している。
Civic Forceのサイト情報によると、第1期は、パートナー団体8団体と協働し、第2期では、復興支援を目的とし、専門性、新規性があり、かつ地元の被災者コミュニティが参加する事業に協働していく。そして今後は地元団体への支援のみを目的とする第3期に入る計画である。
Civic Forceは、富士ゼロックスなどの企業とも協働して、企業が社員ボランティアを組織的に派遣できるプログラムを構築してきた。前述のように、8月には、富士ゼロックスが社員ボランティアを派遣して、検証しながら、9月からグローバルコンパクトのプロジェクトとして立ち上げることができた。Civic Force が受け取った支援金(募金額)は、約10億4000万円(8月10日現在)で、4万9000の個人と法人(寄付金額ベースの割合は個人65%、法人35%)によるものである。
7.企業とNGOの多様な協働プロジェクト――雇用・生産支援へ
現在、震災からの復興へ向けてさまざまなビジョンが提示されている。復興とは町(街)づくり、産業づくり、インフラづくり、エネルギー政策、等々多くの側面がある。最終的にはいかに雇用を造り上げていくかということになる。生産の再開、そのための資金提供のあり方、等々総合的で包括的な視野が必要である。
被災地の人々のビジョンの一例として、前述の「遠野まごころネット」(遠野市被災地支援ネットワーク)が作成した「遠野まごころネットのVision」がある。「遠野まごころネット」は岩手県沿岸部の被災者の方々を支援する遠野市民を中心として結成されたボランティア集団で、ネット内に宿泊場所を設定して個人ボランティアの受け入れを積極的に進めるなど、岩手県では草の根レベルでの活動において、中核的な役割を果たしており、市民社会活動としての新たなる可能性を広げている団体である。
今回の災害を通して、これまでに説明した事例以外でも、多くの多様な協働プロジェクトが企業とNGOとの間で取り組まれている。例えば、被災者が雇用される仕組みづくりである
震災後、行政としてのハローワークは、被災者の失業給付手続き業務で忙殺され、肝心の職業紹介機能が低下した。この状況を受けて、地元に市民組織として設立されたのが「気仙沼復興協会」である。片づけ、雑草取り、見回り、子どもの一時預かり等々、さまざまな仕事に対して日当を提供する、つまり協会が被災者を雇用して仕事をしてもらう形をとっている。協会は給与にあたる資金を市の予算、企業や人々等からの寄付などでまかなう。企業においては、こうした「気仙沼復興協会」のような団体へ寄付することも雇用協力への1手段である。
ロレアル化粧品は、石巻に拠点をもっている緊急支援NGOのJENと協働し、被災建物を賃借・改修して交流センターを開設した。メークや肌マッサージの無料提供、軽食カフェも設置し、運営のために被災者の雇用も図る。被災地の農産物を食べることを促進するための「東日本野菜フェア」を本社ビルなどで開催し(社員による運営)、販売促進を図っている。
また、これは亘理町役場の方から聞いたことだが、これまでの災害ボランティアセンターの活動に対して、NGO・NPOから多くのスタッフ支援があり、非常に役立ったが、今後の再建・復興段階では、工場誘致活動などのために、企業のマネージャークラスの方のボランティア(被災自治体の企業誘致窓口のスタッフとして働く)を必要としている段階にきているという声もあった。
さらに例えば、今後の復興過程での自然エネルギーの事業化への取り組みに当たって、自治体(市)、信用金庫、市民の出資で、「おひさま進歩エネルギー」(飯田市、原亮弘代表)を設立し、幼稚園の屋根に太陽光パネルを設置するというプロジェクトなどがある。企業はこうしたNGOへの資金供与(寄付や投資)は今後の課題であり、重要な役割となる。
国際環境NGOのFoEジャパンによる東北の地域材活用による農漁業復興支援は、東北のスギを使って番屋を建設し、農・漁業コミュニティに提供する。東北では農漁業の復興が生活再建には必須であるからである。