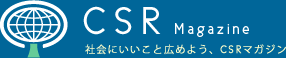「科学技術は環境(エコ)の基本」シリーズ
【第2回】ニュースの中の環境問題と科学技術
~何かしなければの想いを実践につなげる~3.改めて、地球温暖化とは何か?
大島:地球環境問題には、①地球温暖化、②オゾン層破壊、③酸性雨、④生物多様性の減退、⑤森林破壊・砂漠化、⑥海洋汚染、⑦化学物質・有害廃棄物など有りますが、ここでは地球温暖化について取り上げてみましょう。
この100年間、世界の人口は15億人から60億人へと4倍に増大しました。エネルギ-の消費量は20倍、二酸化炭素の排出量は12倍、地球の温暖化が進むのは当然です。過去100年間の気候変化を解き明かし(科学の役割)、気候変化をシミュレ-トする(技術の役割)と実際の変化と一致するとして、IPCC(注)の第4次報告では地球の温暖化は「人為起源の温室効果ガスに起因する」と発表しました。
(注)IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)
重要なポイントは、現在の地球の温暖化は、この「人為起源の温室効果ガスに起因する」ものと「地球自身が数万何単位で歴史的に繰り返す温暖化」が加算されていることをしっかり理解しなければならないということです。科学をしっかり理解することが必要なのです。
「気候変動に関する国際連合枠組条約」(1994年)において、気候変動とは「人間活動が直接又は間接に起因する機構の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生じるものを言う」とあります。また京都議定書(1997年)の中で地球温暖化とは “人の活動に伴う室温効果ガスの排出などで地球の気候システムに危険な撹乱を生じさせるもの”と記され、地球温暖化の言葉は“人の活動に伴う”変動という記述部分に使われています。
すなわち地球温暖化とは、広義の【自然要因】(太陽活動・火山噴火など)+【人為的要因】(工業化の開始:1750年頃以降の室温効果ガスの増加)です。
大陸氷床や氷河が融けるなどは【自然要因】が主原因で【人為的要因】が補助的あるいは加速的原因と考えた方が正しいと言えます。地球温暖化が問題なのは【人為的要因】による温度上昇が【自然要因】より急速に進行し、その変化に生態系や人間の生活活動が追いつけないことにあるのです。
近年、私たちにも地球温暖化対策という言葉は耳慣れたものとなりましたが、本当の意味で我々が地球温暖化への施策を実践しようとするには、そもそも地球温暖化の意味を正確に知る必要があります。
4.地球の気温は2万年前から2~10℃上昇している
大島:地球上に恐竜が出現したのは約2億8000万年前、巨大な植物が茂り温暖期が続いた時代でした。恐竜は6500万年前の寒冷期に絶滅しましたが、その後も地球は常に温暖期と寒冷期を繰り返してきました。約2万年前までマンモスが生存していたことは多くの小学生でも知っていますね。マンモスもまた氷期、寒い時代に絶滅しました。そして、それ以降、地球は多少の寒冷・温暖を繰り返しながら気温が上昇し、現在は2万年前に比べて赤道付近では2℃、高緯度地方では約10℃上昇しているとも言われています。
図-3は35万年前以降の海水準変動を示したものです。約2万年前から現在までに海水準が約120m上昇しているのが分ります。この動きは、この間の気温上昇と一致しています。
図-3 35万年以降の海水変動
このように地球科学の知識を少しだけ勉強するだけでも、地球の温暖化を正しく理解することができます。科学技術というのは決して専門的で難しいものではなく、常に私たちの身近な出来事や現象の中にあり、ちょっとした興味を持つことで基本を理解できるものなのです。
5.“人為的な要因”による温暖化の影響
大島:地球温暖化対策に貢献したいと言っても、私たちには太陽活動や火山噴火など地球規模の温暖化には対応のしようがありません。しかしながら、先ほど申し上げたように、地球温暖化というのは2つの要素があります。【自然要因】と【人為的要因】です。私たちが貢献できるのは【人為的要因】、人間活動が直接または間接に起因する温暖化対策です。
大気中における二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスの増大は、化石燃料の燃焼などによって膨大な量が人為的に排出された結果です。IPCC第4次報告書では過去100年間に地上平均気温は0.74度上昇したことが明らかにされました。日本の主要都市でもこの間に年平均気温が2~3℃高くなっており、これはヒ-トアイランド現象—人為的要因による温暖化の典型的なものです。また最近多発しているハリケ-ンなどにも大きな影響を及ぼしていると考えられます。