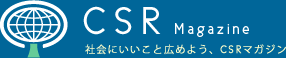識者に聞く
東日本大震災における救援と復興への取り組みPart2[前半]:「企業とNGOの協働」と「進化する日本企業の対応」
拓殖大学国際学部 長坂寿久教授に聞く―物資提供から特定NGOへの資金提供と社員ボランテイア・システムの構築、そして復興(雇用)支援へ4.被災地へいち早く入っていった途上国支援NGO
東日本大震災支援では、従来、海外の開発途上国支援に取り組む多くのNGOが、いち早く東日本に拠点を構え、本格的に救援に取り組んだことも特筆すべき点である。当初、これらのNGOによる被災地支援は、物品提供が中心であった。次第に各NGOは国内の被災地に新たに拠点を構え、炊き出し、泥出し、保健、医療、子どもへの対応など、専門性に応じた多様なテーマごとに、本格的な支援活動に取り組み、定着させていった。具体的には、ピースボート、PARCIC、セーブザチルドレン、国境なき子どもたち、プラン・ジャパン、シャプラニール、第3世界ショップ、ACE(児童労働問題)等々、実に多くの途上国展開のNGOが東日本に拠点を設置している。
こうしたNGOと企業との間にも協働事例が誕生していった。バングラデシュなどアジアで活動している国際協力NGOのシャプラニール(今回の震災を契機に福島県いわき市に拠点を設置)は、当初は救援物資の配付、いわき市勿来地区や小名浜地区での災害ボランティアセンターの立ち上げに協力し、その後、運営に参加している。同団体が実施する生活支援プロジェクト (調理器具一式の提供)では配付物資を企業からの寄付により調達している。
AAR(難民を助ける会)は、仙台と盛岡に事務所を設置し、230以上の企業・団体から協力を得ている。企業との協働の1つとしては、(株)イングラムとの協働で、岩手県、宮城県で炊き出しを行う「ピースプロジェクト」を立ち上げた。これはイングラムの登録商標である「ピースマーク」を用いた商品化を推進し、売り上げの一部が「難民を助ける会」の活動資金として寄付される。
今回の被災地支援では各地の災害ボランティアセンターでのNGO・NPOの働きも見逃せない。NGO・NPOによる今回の震災対応は、NPO法成立後10数年の経験を踏まえて、実に極めてきめ細かく適切なものであった。大震災により、自治体がその機能そのものを大きく損傷したため、多くの自治体で災害ボランティアセンターの設置と対応が遅れがちとなったが、事務局スタッフとして海外で活動するNGOや日本全国の地域のNPOの人材が参加し、ボランティアセンターの活動を支えることになった。さらに、こうしたボランティアセンターには、被災地以外の自治体や、企業から派遣された方々—社員ボランティアも大きく貢献した。