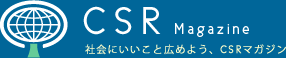識者に聞く
能登半島地震から1年ある介護・福祉施設のふんばり
2024年の元旦に能登半島を襲った震度7の大地震。1年を経たいまも多くの住民が仮設住宅などに身を寄せ、復興の道筋が描けていない。中能登と呼ばれる能登半島の首ねっこに位置する羽咋郡志賀町で6つの介護・福祉施設を運営する社会福祉法人麗心会の理事長藤田隆司さんにこの間の奮闘ぶりを聞いた。[2025年1月1日公開]

震度7の大地震が能登の介護・福祉施設を襲った
福祉施設を襲った甚大な被害
ーー2024年の元旦に大きな地震が能登を襲いました。藤田さんはどこで地震に遭われたのでしょうか。
藤田 その日は冬の能登では珍しいほど穏やかな一日でした。元日とあって施設の利用者の皆さんといつものように初詣にでかけるため私は仕事場に出ていました。初詣も終わり、清々しい気持ちで事務所に戻り、一息ついた午後4時過ぎに大きな地震に見舞われました。それが1回目の地震でした。当法人で唯一木造建築である「グループホーム第二さくらがい」が心配で、そちらに向かったところで2回目の地震が襲ってきました。すさまじい揺れが続き、立っているのもやっとで、利用者に「伏せて」と伝えることしかできませんでした。建物がつぶれ、下敷きになって死んでしまうのではないかと思いました。周りの物が散乱して建物の中はぐちゃぐちゃになりました。
その後、他の事業所からも利用者の安否が次々と届き、幸いにもけが人がいないと聞いてホッとしたのを覚えています。
私どもの施設は海岸から1㎞ほどの場所にあり、津波も心配されました。津波に備えるため、その後、グループホームの方たちとクルマに分乗し、近くの高台へ一時避難しました。
志賀町は、2005年に志賀町と富来町が合併して誕生した町ですが、私どもの施設は旧富来町にあります。旧志賀町には北陸電力志賀原子力発電所が立地しており、万一の場合の不安もよぎりました。地震の直後に県外の友人や知人からたくさん電話がかかってきましたが、安否を伝えるだけで手一杯でした。

ーー施設の責任者というお立場では、利用者の無事だけでなく、職員の安否確認などの対応でもご苦労されたのではありませんか。
藤田 被災当日、私どもの6つの施設には元旦にもかかわらず多くの利用者がいました。「軽費老人ホームのあやめケアセンター」には、定員30名のところ、外泊と入院者を除く25名がいました。認知症高齢者のグループホームの「グループホームさくらがい」には、定員18名中、入院者1名を除く17名がいました。「グループホーム第二さくらがい」には、定員一杯の18名が利用し、地域密着型入居者生活介護の「特別養護老人ホームアイリス」には定員29名のところ入院中の1名を除く28名が、通所介護の「デイサービスセンターアイリス」は、定員30名ですが当日はお休みという状況でした。幸いにもこれらの利用者にけが人はありませんでした。

ーー元旦といっても介護・福祉施設はほぼフル稼働だったわけですね。
藤田 ええ、地震が起きたのは職員が入れ替わる交代の時間帯でした。当日は早番が7名、日勤が2名、遅番が7名の体制で、ちょうど夜間のスタッフが入るタイミングでした。6名の職員と外部委託の調理職員2名が在籍しているときに地震がありました。
発災後、地域の皆さんも津波を心配して高台への避難を急ぎました。当法人の横を通る坂道がその高台につながる道だったので、クルマと歩いて逃げる人でごった返し、道路が渋滞するほどでした。夜になると高台に避難していた人たちも暖を求めて当施設に押し寄せ、94名が当施設で一晩を過ごしました。
当施設の被害は、翌朝までに職員の報告を受けてある程度把握できましたが、私は自分の眼で施設を見て、被害の全様を把握しようとしました。何よりも利用者一人ひとりの安全が心配で、少しでも安全な場所で過ごせるよう、食堂を兼ねたホールに集まってもらうようお願いしました。この地震で正月気分も一気に吹き飛んでしまいましたが、私は妻に1本だけ電話をして無事を確認し、それ以降の10日間は施設で寝泊まりしました。
ーー各施設の被災状況と利用者に及ぼした影響についてもお聞かせください。
藤田 電気・ガスは使える状態でしたが、水は使えなくなり、非常用のペットボトルを倉庫から出して使用しました。水洗トイレが流せなくなって、とても不衛生な環境でした。中庭にあった鯉が泳いでいる池から水をくみ上げて使ったりもしました
建物は床、壁のいたるところにひび割れが生じ、配管が損傷して天井から水が漏れ、暖房設備が使えなくなったところもありました。屋根瓦が落ちて施設の周り中に破片が散乱し、窓ガラスも割れて、ひどいありさまでした。敷地内のアスファルト舗装もいたるところで隆起が起き、安全に通行できない状況でした。
ただ、電気とガスを熱源とする空調設備を備えていた「あやめケアセンター」「グループホームさくらがい」「グループホーム第二さくらがい」の3施設は、暖房が使える状態でした。一番古い施設だった「特別養護老人ホームアイリス」は建築の被害も大きかったため、2日からは被害が少なかった「あやめケアセンター」の食堂に「アイリス」の利用者を避難させました。利用者の不便な生活は10日ほど続き、その後は支援物資でいただいたストーブで暖を取って過ごしていただきました。半年間は野戦病院のような状況が続きました。

ーー施設の被災状況は金額ベースでどれくらいだったのでしょうか。
藤田 地元の業者の方に見積をしていただくと、
*あやめケアセンター 4,640万円
*グループホームさくらがい 560万円
*グループホーム第二さくらがい 162万円
*特別養護老人ホームアイリスとデイサービスセンターアイリス 1億2,790万円
という数字でした。
これは建物の修繕費用の数字で、設備・備品でも別途500万円ほどの費用がかかると言われました。
外部からの支援が復旧・復興のエネルギーに
復旧・復興に向けて一歩ずつ
ーー過疎地の半島で起きた大地震は、復旧・復興にも遅れを生じさせています。この1年の足取りを振り返ってもらえますか。
藤田 私どもの施設は、前身の医療法人の開設から数えると約30年の実績があります。地域に支えられるとともに、地域になくてはならない施設だとの自負がありました。被災当日の夜、大勢の皆さんが私どもの施設なら安心だと避難されてきたことでもそれは分かります。
施設に関わる私どもは、「福祉というものは困った事象が起きた瞬間に手だてをしなければ意味のないものだ」と認識していましたが、その背景にはこの地域で暮らす人々をなんとしても守り抜かなければならないとの強い使命感もありました。
1月2日~5月9日までの間、福祉避難所としての役割を担い、25名の避難者を受け入れたのもそうした思いからでした。

ーー地域や外部の支援が復旧・復興の大きな支えになったようですね。
藤田 発災直後からクラウドファンディングで支援をお願いし、2,000万円を目標に支援をお願いしたところ、5,608,000円の支援が寄せられました。また、それ以外にも寄付という形で900万円を超える支援をいただきました。
その後、私どもが所属する全国老人施設協議会、経営者協議会、志賀町商工観光課からも義援金や支援金を頂戴し、資金面での不安は徐々に解消されつつあります。
現在、日本財団から復旧補助という形で、3,000万円近い補助のお話も進んでいます。また、国からは災害復旧補助ということで、復旧にかかった費用の5/6を補助していただけるとの話もありましたが、これから査定を受けてどれくらい補助していただけるか心配です。
震災直後から友人のネットワークで全国各地から物資が届きましたが、地元では入手できない使い捨ての食器がふんだんに届いて助かりました。日本青年会議所に所属する友人からは、1月4日に水をはじめ、雨漏り対策のブルーシート、凝固剤入りトイレがトレーラーで届き活用させていただきました。

福祉避難所の講習会でご縁が生まれた福祉防災コミュニティーセンターの方からは、発災当日に連絡があり、数日後に施設まで駆けつけてくださり、福祉避難所の運営アドバイスもいただきました。利用者の入浴がままならないという話をすると訪問入浴車を手配してくださり、寝たきりの方の入浴支援で3月まで役立てることができました。あらためて人と人のつながりの尊さを実感しました。
ーー社会福祉法人麗心会の復興は、登山に例えれば何合目くらいでしょうか。
藤田 当施設の復旧・復興に向けた取り組みは、登山に例えれば9合目あたりまで来ています。当施設では利用者を受け入れたままでの修繕工事だったため、工程が複雑となり、それだけ時間を要しましたが、工事は順調に進みました。
空調設備の修繕が遅れていた「特別養護老人ホームアイリス」は、冬場はストーブでしのぎましたが、夏にむけて空調設備が突貫工事で取り付けられました。
屋根の修繕が遅れたため、ブルーシートをかけて雨漏りをしのいできましたが、真夏から小雪が舞う年末までかかったものの、5,000㎡を超える瓦屋根の修繕がほぼ終わりました。復旧工事に尽力された業者の皆さんにあらためて感謝申し上げます。水漏れ修繕など配管設備工事には遠く岩手県や栃木県からも職人の方が工事に駆けつけてくれました。


ーー能登半島は9月の水害被害に加え、余震も続き、いまなお予断を許さない状況です。いま一番心配なことは何でしょうか。
藤田 施設の利用状況はほぼ満床状態が続いています。「デイサービスセンターアイリス」は、震災当初入浴や食事の提供ができず、1カ月サービスを休止しましたが、2月1日にデイサービスを再開したところ、町外に出た避難者も戻って、発災前の利用者数の半数まで回復しました。
私どもが住む地域では、家屋の倒壊で一時は高齢者の数も激減し、「20年後の未来が一度に現れた」と心を痛める毎日でしたが、いまは少しずつ避難者も戻り、利用者が増えて発災前の7割ぐらいの人数になっています。ただ、家を失った方が多いので一時はケアハウスの申し込みが数多く見られます。
私どもがいま一番悩ましいのは職員の確保です。当法人でも、家を失いやむなく当施設を退職した職員が7名います。新しい入職者もあって、どうにか以前に近い形で運営できていますが、高齢化のスピードを考えると、職員の確保は“待ったなし”といえます。先々では外国人労働者の雇用なども視野に入れていますが、従業員の住まい費用の捻出が課題です。高齢化が進むわが国で、福祉の安定を図るためにも、財政面の支援が待たれます。

社会福祉法人麗心会
〒925-0457 石川県羽咋郡志賀町給分ホの3番1
TEL:0767-42-8800 FAX:0767-42-0150
<関連記事>
●負けるな、くじけるな!~能登半島の大規模震災の現地から
●あの能登で原発が動いていたら⁈
●震災から11年、被災地と被災者に3110本の花を!
●東日本大震災から10年。東北から“働く、暮らす、生きる”を問い直す~第9回みちのく復興事業シンポジウから
●「2030年から見た東北」シンポジウム」
●ありがとう さようなら!石原軍団との別れを惜しむ
●障がいのある子どもたちの絵画作品展三菱地所の「キラキラっとアートコンクール優秀賞作品展」
●故・中村哲医師の絵本『カカ・ムラド――ナカムラのおじさん』日本語版が発刊
●第23回大使館員日本語スピーチコンテスト2020
●03-5286ー9090 東京自殺防止センターの取り組み