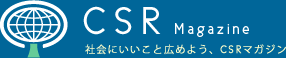CSRフラッシュ
能登に活況が戻るのは、いつだろうか
能登半島地震の被災地・輪島を訪ねて2024年の元旦に発生した能登半島地震。その年の9月には奥能登豪雨が同地を襲いました。地震から1年半が経過したこの6月、奥能登の被災地の復旧・復興を探るため能登・輪島を訪ねました。[2025年7月12日公開]

客足はいまーつでした。
空襲跡のような町が大きな平地にーー輪島「朝市通り」
最初に訪れたのは輪島「朝市通り」。最大震度7を超える地震とその後の火災でほとんどの家屋が焼失した場所です。被災した全249棟が公費解体され、広大な平地が広がっていました。
1000年を超える歴史を誇るとされる輪島の朝市は、一日平均でおよそ2万人が訪れるほどの賑わいの場でもありましたが、いまは見る影もありません。


現在、輪島朝市は、市内の大型商業施設ワイプラザ輪島店の一角を借りて開催される一方、「出張輪島朝市」の名で全国をまわっています。
輪島の朝市は、もとをたどれば近隣の里山で採れた野菜や里海で獲れた魚介類などを持ち寄って集まる素朴な市場でした。ただ、農民や漁民にとっては現金収入を得られる貴重ななりわいの場でもありました。
かつてのような賑わいをいつ取り戻せるかが復興のカギを握ると感じました。

仮設住宅での暮らしを余儀なくされる被災者たち
能登半島地震では281人(災害関連し52人を含む)の尊い命が失われ、全壊7,704棟、半壊9,467棟 (2025年2月16日の内閣府調査) の家屋が損壊しました。また、その後に発生した奥能登豪雨でも16名の死者が出たうえ、全壊41棟、半壊354棟 (2024年10月25日の石川県の調査)の被害が発生しています。
被災住民の多くは、いまも仮設住宅で暮らしています。その数は能登の10市町村の合計で7,168戸とされていますが、輪島市と珠洲市だけでおよそ6割を占め、輪島市が3,161戸、珠洲市が1,740戸となっています。
こうした事情もあって、いまも輪島市の至るところに仮設住宅が見られます。ある仮設住宅を見せてもらうと、夫が定年を迎えたばかりの夫婦が3畳ほどの居室で身を寄せあって暮らしていました。トイレやお風呂は玄関の側に付いており、居間にも小さな台所がありました。地元のローカル紙によれば、独り暮らしの高齢者も多く、5月末までに10人以上が「孤独死」で亡くなったとの報道がありました。

9月の豪雨被害を受けました。

住まいの再建には遠い道のりが
輪島市では、「全壊」から「半壊」と判定された建物が次々と解体されています。しかし、家屋解体の道のりも決して順調ではありません。
高齢化が進む能登では、人的パワーが圧倒的に不足しています。石川県内の事業者だけではとても手が回らず、県外から二次下請け、三次孫請けなどの事業者が駆けつけています。
それは町を走るダンプカーなど作業車のナンバーを見れば歴然です。それこそ北は北海道から南は沖縄までといってよいほど全国各地から人が集まっており、それらの作業車が市内の幹線道路を猛スピードで走るため、市民からは「不安です。いつ事故が起きてもおかしくない」との声を聞きました。
これら解体業者の一部が地元のガソリンスタンドなどで入れたガソリン代金などを踏み倒したまま、いなくなる例も見られるとのことです。

地域外に搬出されています。
いま、輪島市内では、被災住宅の解体が進んでいる地域と進んでいない地域がまだら模様で点在しています。解体が進んでいる地域では空き地が増え、「かつての町並みが分からなくなった」との声も寄せられています。それに伴い住宅の建設価格が急高騰しており、高齢者だけの家庭では住宅建設そのものに二の足を踏む世帯も増えています。
人口流失を食い止め、なりわいの再建を急げ
能登の被災地では、いま人口流出が復旧・復興の足かせになろうとしています。なかでも輪島市と珠洲市からの人口流失は予想を超えて進んでいます。
震災前、輪島市の人口は23,575人(2023年4月1日)でしたが、同市のホームページで最新の人口を見ると20,284人(2025年6月1日)となっています。
しかし、町で市民の声を聞くと、住民票は残しつつも、生活の場を金沢近辺などに移す動きも加速しているようです。「スマホの位置情報などで確認すると親戚や知人の多くが輪島以外の場所にいるのが分かります」と話す人もいました。市民の話では「震災前の3割減がより実態に近いのでは…」と語ってくれました。
背景には、住まいの確保の問題に加えて、仕事探し、子どもの教育の場の確保など複雑な問題が絡んでいるようです。
輪島市内で医療を中心的に担ってきた輪島市民病院においても看護師などの専門スタッフが数多く辞めていると聞きました。輪島市のホームページを見ると職員の募集がトップに登場してきます。
“新・輪島”をめざす「復興まちづくり計画」
2025年2月、輪島市でも「復興まちづくり計画」が発表されました。2つの自然災害で甚大な被害を受けた同市が、復興に向けた指針を示したものです。
この計画では、「復旧期」「再生期」「創造期」に分けた3つの取り組みが掲げられ、およそ10年の歳月をかけて「新・輪島」の実現をめざすとしています。
「復旧期」では、被災者の生活再建に力点が置かれ、①被災者の生活支援と住まいの再建 ②地域コミュニティーの再建 ③子ども・若者に向けた支援を急ぐとしています。
「再生期」では、地域を支えるなりわいの再興をあげ、①伝統文化や自然景観など観光資源の再興 ②農林水産業の再興 ③持続可能な地域経済の再興を掲げています。
「創造期」では、新たなまちへの再生を願い、①将来像を念頭においた市街地の再生②地域の自立と持続可能性を支えるまちづくりの推進 ③防災力の向上と次世代への継承を進めることとしています。
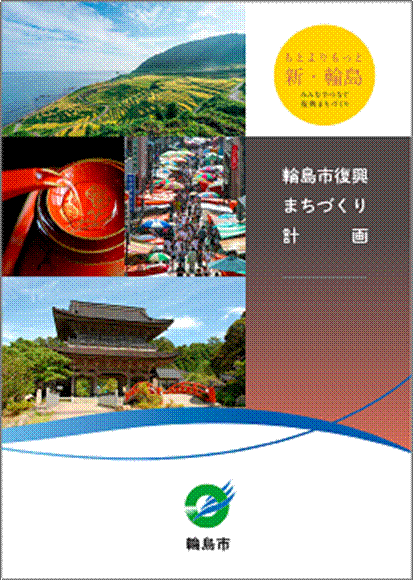
能登半島の先端に位置するとはいえ、輪島市は古くから北前船による交易の恩恵もあり、輪島塗などの地場産業や朝市などの観光資源にも恵まれてきました。ただ、この度の災害により、朝市だけでなく、輪島塗を支えてきた技術の伝承にも黄色信号が灯っています。
能登や輪島の朝市を支えてきたのは元気な女たちだと言われています。一日でも早く輪島が元気を取り戻せるよう、人々の元気を願ってやみません。

輪島港でも大型の浚渫船による海底の掘削が始まっていました。
〔参考資料〕


画像は「石川県ホームページから」借用しています。
<関連記事>
●能登半島地震から1年ある介護・福祉施設のふんばり
●負けるな、くじけるな!~能登半島の大規模震災の現地から
●あの能登で原発が動いていたら⁈
●震災から11年、被災地と被災者に3110本の花を!
●東日本大震災から10年。東北から“働く、暮らす、生きる”を問い直す~第9回みちのく復興事業シンポジウから
●「2030年から見た東北」シンポジウム」
●ありがとう さようなら!石原軍団との別れを惜しむ
●障がいのある子どもたちの絵画作品展三菱地所の「キラキラっとアートコンクール優秀賞作品展」
●故・中村哲医師の絵本『カカ・ムラド――ナカムラのおじさん』日本語版が発刊
●第23回大使館員日本語スピーチコンテスト2020
●03-5286ー9090 東京自殺防止センターの取り組み